 |
虫歯とは? |
 歯の構造 歯の構造 |
 |
まず歯の構造について説明します。歯はお口の中に出ている歯冠という部分と骨の中に埋まっている歯根という部分に分かれます。歯冠部はさらに表面からエナメル質、象牙質、歯髄(歯の神経)という成分から成っています。歯根では象牙質の上を覆っているのがセメント質と呼ばれる組織になります。
エナメル質はほとんどが無機成分からなり、人体の中でで最も硬い組織です。象牙質はやや有機成分が多く、エナメル質よりは硬度が劣ります。また、象牙細管と呼ばれる細い管を通して歯髄とつながっています。ですから、虫歯が進んで象牙質が露出すると、しみたり痛みが出たりするわけです。また、セメント質は本来はお口の中には出ていませんが歯周病が進んだりして、歯肉が下がってくると現れてきます。 |
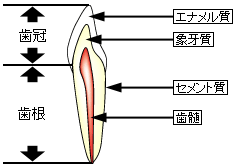 |
|

 虫歯はどうやってできるの? 虫歯はどうやってできるの? |
 |
虫歯とは、お口の中の細菌が、炭水化物(糖質)を栄養源として、産生した酸によって歯が溶けていくといった歯の崩壊を主な変化とする病気のことです。
最近ではさらに特定の細菌が虫歯の発生に関与していることが判明し、虫歯が細菌による感染症であるという考えが広く認識されています。
しかし、その他の感染症と異なり、食生活など、さまざまな環境によってその発症および進行が左右される生活習慣病としての側面も同時にもちあわせている複雑な病気と言えます。
虫歯の原因となる細菌ですが、一種類だけではなく、何種類かの細菌が原因となっているといわれています。ただ、細菌が歯を溶かすには歯にくっついて留まらなければいけません。ミュータンス菌という菌は糖質から多糖体というネバネバした物質を作り出し、それによって歯の表面に留まることができるのです。この多糖体のおかげで他の細菌も歯に留まることができ、ミュータンス菌以外の酸を産生する細菌も虫歯を進行させることができるのです。
また、先ほども説明しましたが、虫歯がエナメル質の範囲にとどまっているうちは痛みを感じません。痛くなってから歯医者に行く方も多いと思いますが、症状が出る頃には虫歯は象牙質にまで達しているのです。 |
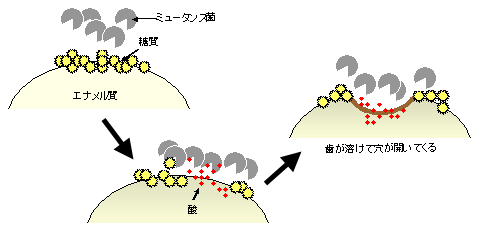 |
|
 |
|
 |